| 「脳死と念仏者の生命観・身体観」 |
< はじめに >
1997年10月、臓器移植法という新しい法律が施行されました。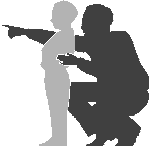
今までは、ドーナーカード(臓器提供意思表示カード)という言葉も、多くの人の知るところとなっています。
この法律によって、生前に文章によって臓器提供の意思の表明をしている人が、脳死と認定されたならば、その人との臓器を移植希望者に提供することが認められるようになりました。
臓器移植以外に救命手段がされている病気に苦しんでいる人々にとっては、待望の法律でした。
したがって回復の見込みがない、脳死状態の人の臓器を移植することによって一人でも多くの人の命が救われるということを[医学の進歩]と手放して賛成する人も大勢います。
しかし法律がつくられたことを契機に、私たちは今までに経験したことのない新しい[いのちの課題]に直面することになりました。
|
< 異なる[いのち]の見方 >
臓器移植という技術は医学における画期的な進歩という一面はありますが、臓器移植による延命を[いのちの操作]という観点から見れば、見過ごすことのできない深刻な問題を内包しています。
つまり臓器移植においては[あるいのちを救う]という目的のために、別のいのちの生と死の境界線が速められたり延ばされたりと自在に[コントロールされる]という、[いのちの尊厳]にかかわる課題があるのです。
それに対し、[釈尊が死について言及されていなかったように、仏教の教えでは生きている時間を問題にしているのであって、生死との境については議論する必要がない]と考える人もいます。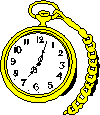
しかし死をみつめることなくして生を見つめることなどありえません。
生を課題にしているということは、言うまでもなく死を課題にしているということなのです。
たしかに、人のいのちを[個体としての生命]と捉える人においては、どうせ遅かれ早かれ生命体として死ぬのだから、少しでも有効な間に(つまり臓器提供できるうちに)死の線引きをした方か良いという理論も成り立っでしょう。
しかし仏教の教えにおいては、人のいのちは独立した固体としての生命ではなく、あらゆるいのちのつながりの中で捉えられています。
仏教は(縁起の教え)を説いてきました。
それは、すべてのいのちは自他一如のつながりにあり、お互いの支え合いの中にあることを示して、一つ一つのいのちの尊さにき付かせ、人間が自らの都合を優先して他のいのちを傷つけることのないようにと教えてきました。
その観点から言えば、本人が了解しているならどのように死をコントロールしても構わないではないかとすることは、様々ないのちの冒涜にもつながります。
ですから、仏教の教えを、例えば報恩行としての捨身の布施や、「改邪抄」の一説である「某 親鸞 閉眼せば、加茂河にいれて魚にあたうべし」(『注釈版』九三七頁)などを部分的、教条的にとりだして、現代の問題領域である脳死問題・臓器移植問題に直接結び付け仏教の教えとの整合性を唱えるのは無責任なものであります。
< 脅かされる「等しく尊いいのち」 >
また、臓器移植によって助かるいのちがあるという、それだけを見ればたしかにすばらしいことです。
しかし実際には、移植を受けるためにかかる費用と手術後も錐続的にかかる莫大な費用を払えるという条件を満たせるのは膨大な数の希望者のうちでもごく限られた人でしかないということも現実的な問題となっています。
等しく尊いいのちにおいても、貧富の差が治療を受けることができるか、否かの分かれ道になりかねません。
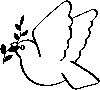 また、すでに臓器移植法が成立している国々では、移植される臓器がすでに商品として売買の対象にもなりつつあり、国際的な臓器の密輸や人身売買といった問題も指摘されています。つまり臓器移植の現場においては、いのちの救済という一面だけではなく、受ける側にも与える側にも「いのちにおける経済問題」がつきまとっているのです。 また、すでに臓器移植法が成立している国々では、移植される臓器がすでに商品として売買の対象にもなりつつあり、国際的な臓器の密輸や人身売買といった問題も指摘されています。つまり臓器移植の現場においては、いのちの救済という一面だけではなく、受ける側にも与える側にも「いのちにおける経済問題」がつきまとっているのです。
その上、有効な人間であるか否かという一方的な価値観に臓器移植がなされることに対し、障害者の団体からも危惧する声があがっています。
概に現実に無脳児や死刑囚からの臓器移植の事例が伝えられているのです。
このように、いのちさえも社会的効率優先主義の天秤にかけられることは、「等しく願われたるいのち」と見る仏教の教えとは相反する差別的ないのちの見方といえるでしょう。
< 人間優先主義を基盤とした生命観の違い >
このような様々な課題や懸念が提起されながらも、この脳死に関わる臓器移植についての反対派の意見が、なかなか人々のコンセンサスをえられない背景には、臓器移植に一線の望みをかけている患者やその家族の方々の心情に対する同情や配慮があります。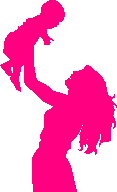
たしかに医療界が声高に問い続けている、移植以外に救命の方法がない患者に対し、余りにも冷酷ではないかという意見や、身近な親族、子供や孫たちがどうしても心臓移植でなければ助からないと言われた人の気持ちが分かるか、と言うような痛切な訴えを無視するわけにはいきません。
しかしながら、私たち仏教の教えをより拠にする者としては、臓器移植論議において当然のごとく受け入れられている、生命観・人間観にたいして異議を唱えざるをえないのです。
今日、日本社会においても寝透している通俗的な人道主義や人間のいのち何よりも尊重され、動物など他のいのちは犠牲になっても構わないと言う考え方、人間のいのちを救うことが何よりも美徳とされる価値観は、親鸞聖人の[一切の有情はみなもって世々生々の父母・兄弟なり〕(『注釈版』八三四房)といういのちのいただきかたとは異なります。
縁起の教えに基づく〔腸りたるいのちを生かさせていただく〕という生命観とも根本的に違うのです。
また、人間とそれ以外の生き物との優劣のみならず、社会的有効性にもとづいていのちの価値をみる〔人のものさし〕にかかれば、短いいのちであるとか病を負と促えることになってしまいます。
この生命観・身体観を根本から問い直すべきではないかと思うのです。
< 念仏者としての課題 >
釈尊以来仏教、常に対機説法という相手の悩みに応じて、またそれぞれの課題を具体的に共に担い、共に支え会う緊張関係の中で発展してきたことを思えば、仏教徒としての見解を提示することだけでなく、苦悩を抱えた人々との歩みの中でこそ念仏の教えが明らかにされていくと言えるでしょう。
ご門主は教書において〔念仏は、私たちがともに人間の苦悩を担い、困難な時代の諸問題に立ちむかおうとする時、いよいよその真実をあらわします〕とお示しになっています。
わたしたち念仏者は、はたして死への恐れや病の苦しみに迷い、愛しい人との別れに苦悩する人々の心のより所となり灯火となるよう仏法を喜び、伝えているだろうか、また支え合い癒される集いの場として寺が開かれているだろうかということを、今一度共に考えてみる必要があるのではないでしょうか。
基幹運動本部専門委員
逸見道郎 |
脳死と臓器移植
< 知られていない脳死 >
〔脳死と臓器移植〕をテーマとする研修会でのできごとです。講師の話が終わり、質疑の時間になったときのことです。参加者が手を拳げ立ち上がりました。
〔私は寝たきりや植物状態になって人に迷惑をかけてまで生きていたくありません。
もう回復できない人のために、どれほどのむだな医療費が使われていることか,脳死の人は、もう脳が死んでいるのですから、死んでいると認めるのは当然のことと考えます。〕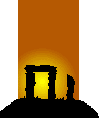
驚いたのはその発言に対して、幾人もの人がうなづいて聞いていたことでした。
先に述べたように〔臓器移植法〕が施行されました。国会での審議も十分とはいえず、移植堆進論者からさえ〔不備の多い法律〕と指摘されている法律です。
しかし、どのようなものであれ法律が施行されたわけですから、〔脳死者〕からの臓器移植に向けての態勢作りが着々と、全国各地の医療機関などを中心に進められています。
それにもかかわらず、〔脳死とはなにか〕ということを本当に理解している人は意外に少ないのではないでしょうか。先の男性のように、〔植物状態〕も〔寝たきり〕も〔脳死〕も同じように見て、〔どうせ間もなく死んでいく人〕というところでくくってしまっている人もいます。
死につつあるのと、死んでいるのは明らかに違うのですから、その差異を明らかにしなければ、私たちはとんでもない過ちをおかしてしまうかも知れません。
< 人の死とは >
人がどのようになったことをもって死とするかということは、実に簡単なようで大変むつかしい問題を含んでいます。
さまざまな試行錯誤を経て、現在の死の三徴候説の判定が広く行われるようになりました。
つまり、心臓の停止、呼吸の停止、瞳孔の散大固定の診断によって、死と認めるわけです。それでも、医師から死を宣告されたからといって、苦楽をともにしてきた家族にとってはその肉体が瞬時に死体という〔物体〕に変わったと受けとめることはできません。
だんだん冷たくなっていく手や足をさすりながら、悲しみのなかで家族は少しずつその死を受け入れていくのです。
< 脳死とは >
人は死への過程のなかで必ず脳の死を通過することになりますが、いま問題となっている〔脳死〕は、自然な状態のなかでは起こり得ないものです。
人工呼吸器など生命維持装置の発達によって初めて起きたのですから、脳死は高度な医療施設なかでのみ起きるといってもよいでしょう。
法律では〔脳死〕そのものを簡潔に説明せずに、〔脳死した者の身体〕というところで規定しています。『脳死した者の身体』とは、①『移植術に使用されるための臓器が適出されることとなる者』であり、②『脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたもの』となっています。
脳死をひとの死とするという判断を法律は下していません。
脳幹を含む全脳の不可逆的な機能停止であっても、移植のために臓器が摘出される身体は死体、摘出されない身体は死体とはならないというきわめて便宜的な判断です。
また、「脳死」ということばそのものが押しつけてくるイメージを整理してみなければなりません。
「脳死というのだから死である」というのは、あまりにも乱暴な結論です。
医療機関においてさえ、「脳死」ということばが安易に使われすぎているように思います。生命維持装置につながれている重篤の患者の病状説明に、【脳死】【脳死に近い状態】【脳死状態】ということばが曖昧に使われている例の多いことも指摘されています。
たとえ専門医によって脳死と判定されたとしても、心臓は拍勤しています。休も暖かいのです。
身近なひとがそのようになったとしても、私たちはその体を死体とみなすことができるものでしようか。
< 脳死をひとの死とすることの危なさ
>
いわゆる【脳死患者】生命維持装置をつけても、そう長く生きることはできないといわれています。長く生きられない【脳死者】をなぜ「人の死」としたいかというと、臓器移植が目的としてあるからです。
特に心臓移植は、脳死をひとの死としない限り不可能な医療です。
他の臓器についても、【新鮮な臓器】がほしいという欲求があります。
ここには、生命を利用価値でみていこうとする危なさがあることを見のがすべきではありません。
脳死をひとの死としようとする根拠に生命の有機的統一を司る器官は脳であるとしてその機能停止は死であるとする見解があります。
こういう思想の行きつく先は人間の知的活動にとらわれるあまりに、無脳児や植物状態のひとなど、精神活動の低下した人間を「死んだも同然」として、切り捨てていく方向に流れていくように思えてなりません。
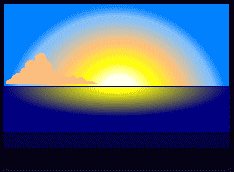 事実、無脳児から「生きたまま」臓器が摘出され移植された例が報告されています。 事実、無脳児から「生きたまま」臓器が摘出され移植された例が報告されています。
「脳死」と臓器移植は、本来別なものですが、いま、臓器移植をぬきにして脳死を論じることはできません。
その臓器移植は、バラ色の医療なのでしようか。
誰のための医療なのでしょうか。世界的に慢性的な臓器不足が続いています。
そこから、「臓器をめぐる犯罪」が多発しているといわれています。
ひとの死を待つ医療が、ほんとうに健康的な医療といえるのでしょうか。
そして、結局は移植医療は弱者のための医療とはならないでしょう。
世界で最初の心臓移植が行われた南アフリカでは、初めの九例、ドナー『臓器提供者』はすべて黒人、レシペェント『臓器を受ける患者』はすべて白人でした。
貧困につけこんで臓器を買う人がいる現実もあります。
障害者をはじめ、社会的弱者がドナーとならざるおえない状況に追い込まれていく危険性が十分にありえるのです。
また、多額の医療費を支払ってレシペェントになることができるのは、限られた人しかなれないという心配もあります。
不老不死一古代から人類が抱きつづけてきたあくなき願いです。医療の世界では、死を敗北と考えてその克服に力を注いできました。
特に現代は、医療技術や生命科学の発達によって、生命そのものに対してこれまでには思いもよらなぬ操作が可能となってきています。そのひとつが臓器移植です。
そして、臓器移植を可態にしていくひとつの便法として、『脳死』が作られていく-これが臓器移植法のもう一方の顔であるともいえましょう。
釈尊は、生命のありようについて『人、世間愛欲のなかにありて、独り生れ独り死し、独り去り独り来る』(『注釈版聖典』五六頁)と示されています。
「代るものあることなし」(『注釈飯聖典』五六頁)とも教えられました。
それは、ひとは死すべきものとしてあり、誰に代ってもらうこともできない厳しい現実を受けめよとのよびかけではなかったでしょうか。 |
|